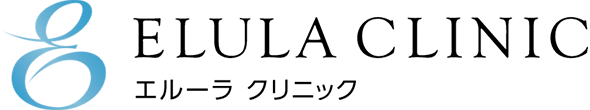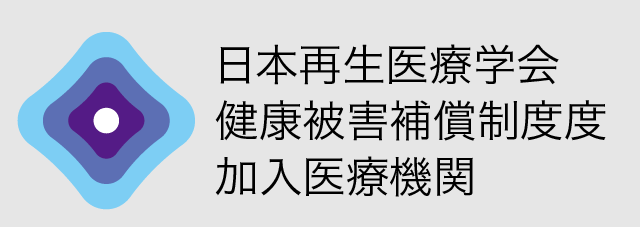皮膚科

土日に保険皮膚科診療
エルーラクリニックは働く人の味方です
土日に皮膚科疾患にかかった場合、どこで治療してもらったらいいのでしょう。
どうして、土日に普通の保険診療を行っている皮膚科が存在しないのでしょう。このような疑問を持ったことから、土日に保険皮膚科診療を行うことにしました。
アトピー性皮膚炎・にきび・蕁麻疹のような慢性疾患から、帯状疱疹・ケガ・虫刺されのような急性疾患まで皮膚科には多種多様な疾患が存在します。救急病院に行くような疾患ではないけれど、月曜日は待てない。
エルーラクリニックは、そんな働くあなたの味方です。もちろん、救急対応が必要な皮膚疾患は専門病院へご紹介させていただきます。
高齢の方でも、お子様でも、どなたでも土日皮膚科を受診していただくことは可能です。こんなことで受診して大丈夫かなと思う必要ありません。放っておくと重症化する皮膚疾患もあるのです。遠慮せずに、お気軽にエルーラクリニックを受診してください。
診察可能な疾患

アトピー性皮膚炎、ニキビ、蕁麻疹、
多汗症などの慢性疾患
皮膚疾患に応じた処方を提案させていただきます。皮膚疾患の原因を確認し、状態を把握した上でベスト治療を開始していきます。
状況に応じてアレルギー検査を行います。
軟膏や一般の内服薬だけでなく、本院では漢方薬も使用しながら治療させていただきます。

帯状疱疹、虫刺され、熱傷などの急性疾患
巻き爪、切り傷、皮下膿瘍形成にも対応
土日のような休みの日に帯状疱疹(ヘルペス)や虫刺されなどの急性皮膚疾患にかかった場合、これまでは治療するところがありませんでした。放っておくと悪化する場合もあるのが急性皮膚疾患です。
帯状疱疹は、治療が遅れると疼痛が増悪し湿疹の悪化をきたします。また疼痛の増悪や帯状疱疹後の神経痛が長期持続してしまう可能性があります。
まずはお早めにエルーラクリニックを受診ください。

水虫・イボなどの感染性疾患
粉瘤、巻き爪等に伴う爪囲炎
感染性皮膚疾患は、周りの人にうつしてしまう可能性もあるので、できる限り早めに直してしまう必要があります。水虫などはなかなか治りにくい皮膚疾患でもあるので、エルーラクリニックで一緒に治療を行いましょう。
イボ(疣贅)はヒトパピローマウイルスポックスウイルス等の感染によるできものです。外用療法・内服療法・凍結療法等で加療させていただきます。
できる検査

ダーモスコピー検査
湿疹を虫眼鏡や顕微鏡で拡大して観察することにより、正確な診断をすることができます。

一般採血検査・アレルギー検査
花粉、ハウスダスト、食べ物、金属などアレルギーの抗原検査を血液検査で調べることができます。
接触性皮膚炎の場合にはパッチテストが必要なこともあります。
にきび(尋常性ざ瘡)
尋常性ざ瘡は、毛根を包んでいる袋状の組織である毛のうを中心とした炎症性疾患です。毛のうの一部からは毛が生えていますが、毛が抜け落ちて“さや”だけになったものも多くあります。毛のうには脂腺という皮脂を出す腺が存在していて、内部に脂を充満させています。特に思春期になると、この皮脂分泌が活発になって毛のうを埋め尽くし、角栓等で毛のうが詰まっていた場合、この皮脂が排泄されず溜まって皮膚表面に盛り上がるようになってしまいます。これが「白にきび」といわれるものです。
治療としては、皮膚を洗浄し清潔に保ち、毛のうの出口を開放するアダパレン(ディフェリン)や角質剥離や抗菌作用を持つ過酸化ベンゾイル(ベピオ)等の使用が必要となります。感染を伴っている「にきび
」に対しては抗生剤の使用も併用していきます。ただし、いずれの薬剤もある程度の刺激感があり、顔が赤くなったりかさかさしたりしますので、最初は塗るエリアや回数を減らすなどの工夫が必要なこともあります。なお、アダパレンは妊娠している女性や妊娠している可能性のある女性には使えませんので注意してください。症状が非常に強く、膿疱(皮膚に膿がたまったもの)が多発しているような患者さんには抗生剤の内服が必要なこともあります。本院では、体質改善も含め漢方薬の処方も併用することも可能です。
痒疹
痒疹は強いかゆみがある皮疹で、虫刺されなどの急性痒疹と慢性痒疹に分類されます。急性痒疹はステロイド外用療法や抗ヒスタミン薬内服で改善します。一方、慢性痒疹は数週間から数ヶ月持続します。慢性痒疹には、結節状の皮疹が特徴のである結節性痒疹と蕁麻疹様湿疹様紅斑がでる多形慢性痒疹に分類されます。虫刺症や肌の乾燥、アトピー性皮膚炎、内科疾患などを契機に出現し慢性化します。上記の加療で改善しない難治例には光線療法や免疫抑制剤、生物学的製剤(デュピクセント®:15歳以上、ミチーガ®:13歳以上)が有用です。
蕁麻疹
蕁麻疹の多くは、数時間~24時間で痕を残さず自然に消失します。ただし、以下のような場合は、医療機関での診断・治療が必要です。
・かゆみや痛みの症状が強い
・膨疹が広範囲に及んでいる
・原因が分からないが繰り返し症状が現れる、あるいは、症状が長引いている
・蕁麻疹だけでなく、まぶたや唇、喉のはれ、呼吸困難を伴っている
蕁麻疹の診断では、まず食べたもの、常用薬、受けた刺激、既往症などの問診を行い、必要に応じて血液検査・アレルギー検査などをして、直接的な原因や蕁麻疹のタイプを探ります。
ただし、検査をしても原因が特定できるケースは稀です。検査によって特定の原因物質や刺激(食物、薬品、物理的刺激など)が分かった場合はそれらを避けて生活するようにします。
蕁麻疹の治療は、医療機関での抗ヒスタミン薬内服治療が基本です。症状が強い場合や患部が湿疹化した場合はステロイド外用剤を併用して患部を治療します。
蕁麻疹のタイプには「アレルギー性蕁麻疹」、「非アレルギー性蕁麻疹(物理性蕁麻疹)、(コリン性蕁麻疹)」などがあります。
・アレルギー性蕁麻疹
食物、薬品、植物などに含まれる特定物質(アレルゲン)に反応して起こります。通常アレルギーの原因物質を食べたり、それらに触れたりした数分後~1、2時間後に症状が出ます。
・物理性蕁麻疹(機械性、寒冷、温熱、日光など)
・コリン性蕁麻疹
発汗する、もしくは発汗を促す刺激に伴って、3~5mm大の小さい膨疹または紅斑(こうはん)がたくさん現れるのが特徴です。左右対称に症状が現れることもあります。
それぞれの膨疹はくっつくこともありますが、他のタイプの蕁麻疹のように、地図状や扁平な膨疹になることはありません。かゆみ以外に、ピリピリ・チクチクした痛みを伴うことが多いのも、他のタイプの蕁麻疹と異なる特徴です。
コリン性蕁麻疹は、運動不足や入浴時に湯船につからないなど、汗をあまりかかない生活習慣をきっかけに発症するケースが報告されています。普段から適度に汗をかくことが、コリン性蕁麻疹の発症予防に役立つことがあります。ただし、すでに発症している場合は、無理に汗をかくと症状を悪化させる恐れがあるため、必ず医師に相談するようにしてください。
コリン性蕁麻疹は、稀に無汗症(汗が出ない病気)やアナフィラキシーなどの重篤な病気に進展することもあります
慢性蕁麻疹
多剤内服加療でもコントロールが難しい慢性蕁麻疹には、免疫抑制剤やステロイド内服、デュピクセント®(抗ヒトIL−4/13受容体モノクローナル抗体、12歳以上)やゾレア®(抗ヒトIgEモノクローナル抗体)による加療をしております。
化膿性汗腺炎
化膿性汗腺炎は難治性のアクネや吹き出ものと勘違いされていることが多く、慢性の毛包に生じる炎症性疾患です。臀部や外陰部、腋窩などに有痛性の皮下結節を繰り返し、瘢痕を残してしまいます。化膿性汗腺炎の一つである臀部慢性膿皮症は特に喫煙者には高頻度で有棘細胞癌を合併することもあります。また、化膿性汗腺炎には糖尿病の高頻度で合併し、他の消化器疾患の合併で膿瘍病変を形成することもあります。まずは採血、細菌培養、画像検査、便検査をお勧めします。治療は抗生剤内服やステロイド外用でコントロールし、難治例はヒュミラ®が保険適応されており大変著効します。
アトピー性皮膚炎
アトピー性皮膚炎は、皮膚症状が悪くなったり改善したりをくり返し、強いかゆみのある湿疹が認められ、そして「アトピー素因」をもちます。
アトピー素因とは①家族にぜん息、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、アトピー性皮膚炎にかかったことがあるか患者さん自身がいずれか、あるいは複数にかかったことがある。もしくは
② IgE抗体ができやすいことをいいます。
アトピー性皮膚炎の患者さんは皮膚のバリア機能が低下しており、さまざまな刺激に皮膚が反応して炎症が生じやすくなります。皮疹の広がり方は小児と成人では異なるという特徴があります。皮膚から水分が失われやすくなるために、乾燥肌の患者さんが多いこともアトピー性皮膚炎の特徴です。
治療は、皮膚の保湿と抗ヒスタミン剤によるかゆみの抑制が基本となります。これに追加で抗炎症性外用薬(ステロイド軟膏、タクロリムス外用薬)を塗布し加療します。外用薬の効果が不十分な場合にはアトピー性皮膚炎の悪化因子となるサイトカインという物質をブロックすることで症状を改善させる生物学的製剤が保険適用となっています。
外用治療でコントロールが難しい場合は、光線療法や短期免疫抑制剤、生物学的製剤(デュピクセント®:生後6ヶ月以上、ミチーガ®:抗ヒトIL-31受容体Aモノクローナル抗体)6歳以上、アドトラーザ®:抗ヒトIL-13モノクローナル抗体 15歳以上など)、JAK阻害薬などで加療します。
帯状疱疹
帯状疱疹の原因は 幼少時に罹患した水ぼうそうと同じウイルスで、このウイルスが日本人の成人90%以上の体内(神経節)に潜んでいます。
加齢や疲労、ストレス、疾患等で免疫機能が下がると、ウイルスが活性化して帯状疱疹を発症することがあります1)。
50歳代から発症率が高くなり、80歳までに約3人に1人が発症すると言われています2)。50歳以上の人は、帯状疱疹の予防接種を受けることができます。50歳以上は帯状疱疹の発症率が高くなる傾向3)がありますので、ワクチン予防接種は帯状疱疹を発症しないための選択肢のひとつになります。現在2種類あります(生ワクチン、不活化ワクチン)。効果等にも違いがあり相談させていただきます。
1)
国立感染症研究所: 帯状疱疹ワクチン ファクトシート 平成29(2017)年2月10日
2)
Shiraki K. et al.: Open Forum Infect Dis. 4(1),
ofx007, 2017
3) Shiraki K. et al.: Open Forum Infect Dis. 4(1), ofx007, 2017
帯状疱疹は内服加療が可能な疾患ですが、顔面発症や汎発性帯状疱疹、免疫抑制状態下の帯状疱疹は重症化することがあります。治療開始が遅れると、治療後に神経痛や神経障害が長期間継続する場合があります。視神経や脳神経内への感染により重症化する場合は入院にて抗ウイルス薬点滴加療をいたします。失明、神経後遺症、致死的な状態に陥ることもあります。
よって有痛性の発赤を伴う発疹を認めた場合には、帯状疱疹も疑い早期の受診をおすすめいたします。
単純疱疹(口唇ヘルペス・性器ヘルペス)
単純ヘルペスウイルス(HSV)は感染力が強く、接触感染します。直接的な感染の他に、ウイルスがついたタオルや食器などを介しても感染します。単純疱疹の再発しやすさは場合によって違いますが、たとえば単純ヘルペスウイルス2型による性器ヘルペスは1年以内にほぼ確実に再発します。ヘルペスの治療にはいくつかの選択肢があり、それぞれアプローチが異なります。
治療法は、以下の3種類に分けられます。
- 一般的な治療:発症時の一般的な対症療法(抗ウイルス薬の内服投与や軟膏の使用)
- PIT療法:再発の予兆や初期症状に応じて患者自身の判断で内服ができる治療法(前もって抗ウイルス薬を処方し携帯しておく)
- 再発抑制療法:長期の内服を続けることで再発を防止する治療法
乾癬、乾癬性関節炎
尋常性乾癬とは乾癬とも言います。慢性の皮膚疾患で、国内における有病率は1000人中1~2人くらいといわれています。感染とは違うので、他人にはうつりません。
卵や手の平くらいの大きさの赤い発疹が体のあちこちにできてくる皮膚病です。赤い斑点に加えて白いかさぶたのようなものがはがれてきます(写真1、2)。特にできやすい場所は、ひじ・ひざ・頭・背中です(図1)。半分くらいの患者さんにはかゆみがあります。爪の変形や関節の痛みを伴うこともあります。状態が良くなったり悪くなったりを繰り返します。
なぜ発症するかはまだ分かっていません。最近の研究から、何らかの原因で皮膚の表皮細胞が異常に増殖し、そこに免疫の異常が加わって炎症が起きると考えられています。また外傷・感染・ストレス・薬剤などがきっかけになり、糖尿病・高脂血症・肥満などのメタボリック症候群が基礎にあることが多いといわれています。多くの場合は、肉眼的に診察することで診断が可能です。ただそれだけで難しい場合には、病理検査をすることもあります。これは皮膚を小さく切り取って詳しく調べる検査です。
最近、乾癬の病態や治療についての研究が急速に進んできました。その結果、治療方法の選択の幅がとても広くなっています。
治療方法は大きく分けて、外用療法、光線療法、内服療法、注射療法があります(図2、表)。
①外用療法
外用療法には、ステロイド外用剤、ビタミンD3外用剤(オキサール®️)、ステロイドとビタミンD3の配合剤があります。これらの薬は軽症から中等症の乾癬に使われます。ステロイド外用剤では皮膚が薄くなったり血管拡張がみられることがあります。ビタミンD3外用剤ではヒリヒリ感がみられることがあります。
②光線療法
光線療法はナローバンドUVB、エキシマライト、PUVAがあります。ナローバンドUVBは311nmの波長の紫外線を全身の皮膚に照射する方法です。エキシマライトは308nmの波長の紫外線を皮膚に照射する方法です。手・足・爪など範囲の狭い場合に使用されます。③内服療法
内服療法には、シクロスポリンとエトレチナートとアプレミラストとメトトレキサートがあります。中等症から重症の乾癬に使われます。シクロスポリンは免疫抑制剤の1つです。副作用としては腎障害や高血圧などがあります。エトレチナートはビタミンA誘導体です。この薬は催奇形性あるため、服用中と服用後しばらく(女性は2年、男性は6か月)は避妊しなければなりません。
④注射療法
注射療法には生物学的製剤が使用されています。生物学的製剤には表に示した8種類の製剤があります。中等度から重症の乾癬に使われます。インフリキシマブ、アダリムマブ、セルトリズマブはTNF-αに対する抗体、ウステキヌマブはIL-12/23p40に対する抗体、グセルクマブとリサンキズマブはIL-23p19に対する抗体、セクキヌマブとイキセキズマブはIL-17Aに対する抗体、ブロダルマブはIL-17A受容体に対する抗体です。副作用として結核・肺炎・肝炎・炎症性腸疾患などを発症することがあります。
外用療法に加え、内服薬(チガソン®、オテズラ®、ソーティクツなど)や光線療法での加療が可能です。重症な乾癬、乾癬性関節炎には関節変形が生じる前に発症早期に生物学的製剤やJAK阻害薬での加療が必要です。
膿疱性乾癬
チガソン®、生物学的製剤だけでなく、急性増悪時には入院加療にて顆粒球単球吸着除去療法やスペビゴ®(抗ヒトIL-36レセプター抗体)の併用も考えます(保険適応)。
原発性多汗症
汗をかきやすい体質と思っていませんか。日常生活に支障をきたすほどの発汗が腋窩、手、足底部ある場合は治療対象になります。続発性多汗症の鑑別には、採血や画像検査が必要になります。原発性多汗症の治療として、手掌にはアポハイド®️ローションが、腋窩にはエクロックゲル®、ラピフォートワイプ®が使用できます。重度の腋窩多汗症には保険適応があるボトックス注射が有用です。全身多汗症でお困りの方にはプロバンサイン®の内服が適応されます。
腫瘍性病変
腫瘍性病変の診断には、ダーモスコピー、超音波検査などを用いて診断します。悪性を疑う場合には、腫瘍の一部を生検して病理診断が必要となってきます。連携病院紹介し、病理検査等を行い治療方針が決定されます。
掌蹠膿瘍症
「掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)」とは、手のひらや足のうらに、水疱や膿疱がくり返しできる病気です。膿疱の中には細菌やウイルスなどの病原体は入っていないため無菌性膿疱で、直接触れても人に感染することはありません。他に爪が変形したり、骨や関節(胸骨、鎖骨、肋骨及びその周辺部位や結合部)に発症することが多い)が痛んだりすることもあります。
特徴的な水疱は、できはじめにかゆみを伴うことが多く、しばらくすると膿疱が乾いて茶色っぽいかさぶた[痂皮(かひ)]となり、はがれ落ちます。まわりの皮膚にも炎症がおよんで赤くなる紅斑や皮膚表面がカサカサと肥厚し魚の鱗様の鱗屑や角層がつみ重なって厚くなると、歩くたびにひび割れて痛みを生じます。
掌蹠膿疱症の原因は明らかではありませんが、何らかの原因により炎症を起こすサイトカインが過剰に産生されてしまい、本来、異物を排除するための防御反応が必要以上に起きてしまうことによってさまざまな皮膚症状があらわれるのではないかと考えられています。
刺激によって悪化することがあるため(ケブネル現象)、皮をめくったり水疱を潰したりすることは絶対にやめましょう。
治療は先ずは生活習慣の見直しです。原因に喫煙、扁桃炎、副鼻腔炎、歯周炎などの病巣感染が無症状で発症に関わることが多いと報告されています。掌蹠膿疱症の患者様の約70~90%に関与があると報告され3)、禁煙、これら疾患の精査・加療で症状の改善、治癒が得られています。また金属アレルギーの関与も報告されており注意が必要です。
3)日本皮膚科学会掌蹠膿疱症診療の手引き策定委員会: 日皮会誌, 132, 9: 2055-2113(2022)
水イボ(伝染性軟属腫)
1~5mm(まれに1cm 程度のこともある)程度の常色~白~淡紅色の丘しん、小結節(しこり)。
表面はつやがあって、一見水ほう(水ぶくれ)にも見える。
大き目の結節(しこり)では中心が凹になっている。
多くの場合では、数個~数十個が集まっている。
四肢、体幹等によくみられるが、顔、首、陰部等どこにでも生じる。
原因は伝染性軟属腫ウイルス(ポックス ウイルスの一種)
専用のピンセットでの摘除法(痛みと少量の出血があるため、局所麻酔薬テープを事前に貼ることがある)、外用療法、内服療法、冷凍凝固療法等がある。
皮膚の清潔を保ち、保湿剤等でバリア機能を改善する。
皮膚のバリア機能が未熟な乳幼児、アトピー性皮膚炎患者等では、水いぼ(伝染性軟属腫)を引っかいた手で別の箇所をさわることで、感染が拡大し、広い範囲に水いぼ(伝染性軟属腫)が生じる場合があるため。
伝染性軟属腫(水いぼ)を衣類、包帯、耐水性ばんそうこう等で覆い、他のこどもへの感染を防ぐ。
また、プール後は皮膚表面のバリア機能が低下しやすいので、皮膚の保湿を保つ。
接触感染により感染するため、日常的に手洗いの励行等の一般的な予防法を実施することが重要である。
尋常性疣贅
ヒトパピローマウイルス(HPV)は、イボの原因になります。皮膚のイボは傷ついた皮膚にHPV2型が侵入し3~6ヶ月かけて形成されます。表面が細かな顆粒が集族した突起物として確認されます。刺激やイボ表面の損傷に伴い徐々に大きくなってきます。イボをむやみに触らないようにしましょう。感染力はそれほど強くありません。治療は、液体窒素を使用っした凍結療法が第一選択となります。ただし1回の治療では治癒せず、数回の治療が必要となってきます。他に手術的に切除する電気焼灼療法もありますが、中途半端な切除を行うとかえって大きなイボになることが有るため注意が必要です。
HPVの中には皮膚にイボを作り出すものもあれば、性器のイボ(腟、陰茎、または直腸の内部や周囲に生じるできもので、尖圭コンジローマと呼ばれます)の原因になるものもあります。一部の種類のHPVに感染すると、がんになることもあります。HPVは性感染症の原因にもなります。
ヒトパピローマウイルス(HPV)の種類が違えば、引き起こされる感染症も異なります。例えば、性器にできる、目で見て確認しやすいイボもあれば、子宮頸部、腟、外陰部、尿道、陰茎、肛門にできる見えにくいイボもあり、さらに皮膚のイボもよくみられます。
性器にできるイボ(尖圭コンジローマ)は、急速に増大し、焼けるような痛みを引き起こすことがあります。
一部の種類のHPVに感染すると、子宮頸部、腟、外陰部、陰茎、肛門、のどのがんのリスクが高まります。
見て確認できる性器疣贅は外観から特定し、見えにくいものについては子宮頸部と肛門を調べます。
ワクチン接種により、がんの原因になるほとんどの種類のHPV感染症を予防することができます。
視認できる性器疣贅はレーザーや凍結(凍結療法)または手術で取り除くことが多く、ときには薬を塗る治療も行われます。
HPV感染症は最もよくみられる性感染症(STI)です。HPVは非常によくみられるため、ワクチン接種を受けていない性的に活動的な男女の約80%が、生涯のどこかの時点で、このウイルスに感染します。米国では毎年約1400万人が新たにHPVに感染しています。HPVワクチンが利用できるようになる前は、毎年約34万~36万人の患者がHPVによる尖圭コンジローマのために受診していました。HPVの予防接種を受ける人が増えるにつれて、HPV感染症の所見がみられる人の割合は減少しています。
大半の感染症は1~2年で治りますが、長引くものもあります。一部の種類のHPVによる感染が長引くと、ある種のがんのリスクが高まることがあります。
HPVは100種類以上あることが知られています。よくみられる皮膚のイボを引き起こすタイプもあれば、以下のように様々な性器感染症を引き起こすタイプもあります。
体の外側にできる(見えやすい)尖圭コンジローマ:このようなイボは特定のHPV、特に6型と11型により生じます。6型と11型ががんを引き起こす可能性は低いです。これらの型は性行為で伝染し、陰部や肛門部に感染します。
体の内側にできる(見えにくい)尖圭コンジローマ:他のタイプのHPV、特に16型や18型は陰部に感染しますが、見えやすいイボを引き起こすことはありません。この型では、子宮頸部や肛門に小さく平らないぼができますが、これはコルポスコープ(腟拡大鏡)と呼ばれる器具でしか見ることができません。いぼは腟、外陰部、尿道、陰茎、肛門、またはのどにも発生する場合があります。このような見えにくいところにイボがある場合、通常は症状がみられませんが、これを引き起こすタイプのHPVは、子宮頸がん、腟がん、外陰がん、陰茎がん、肛門がん、膀胱がん、一部の頭頸部がん、のどのがんの発生リスクを高めます。そのため、このようないぼを治療する必要があります。ヒト免疫不全ウイルス(HIV)に感染していると、HPV関連のがんを発症するリスクが高まります。
性器や直腸領域に影響を及ぼす種類のHPVは通常、腟または肛門性交を介して感染しますが、他の感染経路を介しても広がります。
HPVはオーラルセックスでも感染し、口の感染症を引き起こして口腔がんのリスクを高めます。
AGA(男性型脱毛症)
AGAとは、「Androgenetic
Alopecia」を略したもので、「Androgenetic」は「男性ホルモン」、「alopecia」は「脱毛症」のことを意味します。
AGAの原因は正常な毛髪のサイクルの乱れにあります。AGAの患者様はこの毛周期が早くなっており、毛髪が成長する前に抜け落ちてしまっているのです。実はこのサイクルを乱す物質が存在し、これが男性ホルモンの「テストステロン」が変化した「DHT(ジヒドロテストステロン)」なのです。
治療薬には、内服薬と外用薬があり、薄毛の進行レベルに合わせて処方されます。内服薬には、次のような種類があります。DHTの生成を抑制する内服薬がフィナステリド錠(プロペシアジェネリック)、デュタステリド(ザガーロ)となります。頭皮の血流改善薬としてミノキシジル内服薬とフロジン外用薬があります。
他に最新の治療として幹細胞培養上清液/PRPを頭皮へ注射投与し毛母細胞の機能改善・活性化を促す再生医療もあります。
自己免疫性水疱症
ステロイド内服が第一選択ですが、重症、難治性の水疱症は入院適応になります。患者さんの年齢や健康状態を考慮し、免疫抑制剤併用やステロイドパルス治療、二重濾過膜血漿交換療法、免疫グロブリン大量静注療法を施行しております。に文章を入力してください
粉瘤(アテローム)
皮下にできる良性腫瘍で、皮膚の上皮(表皮や外毛根鞘)が皮内や皮下に袋状の構造を形成したもので、半球状の隆起として触れることが多いです。袋の内側が上皮ですので、本来は外に脱落するはずの角質(いわゆる垢)や皮脂が粥状の内容物として袋内に蓄積し、少しずつ大きくなっていきます。皮膚の老廃物のかたまりで、腫瘤の中央にしばしば見られる小さな黒っぽい開口部から、悪臭を伴う内容物がでてくることがあります。
身体のどこにでもでき、特に背中やうなじ、頬、耳たぶなどにできやすい傾向があります。
細菌感染を起こして急にその大きさを増し、赤く腫れて痛みを伴ったり、皮膚が破けて膿汁と臭い粥状の内容物が排出されたりします。
治療は袋状の嚢胞壁(上皮)を内容物ごと一塊にして取り除くことで治癒します。
内容物を落ちだすだけでは必ず再発します。
小さいものは局所麻酔下に切除摘出することが一般的ですが、大きかったり感染が合併している場合には2期的に加療することが多いです。初回は抗生物質を併用しながら、切開し内容物を除去し粉瘤を先ず小さくします。その後一塊に切除摘出します。この方が術創も小さく目立たずに治癒します。いずれにせよ、小さな段階で処置した方が早く症状の改善が得られますのでご相談ください。
手術法 --- 局所麻酔下に切除摘出可能です
①くり抜き手術:近年腫瘤の手術方法です。直径4mmほどの円形切開を粉瘤の中心部皮膚に加えて、粉瘤内容を押し出したのち原因となる袋状組織を剥離摘出してしまいま す。完全に摘出することで再発せず、傷も殆ど目立たずに治癒します。
②紡錘状切開摘出術:以前より施行されていた手術法で、粉瘤直上に紡錘型に皮膚切開を加えて炎症性粉瘤を切除摘出する方法です。極端に大きな粉瘤や著しく炎症を起こした粉瘤に対し適応となる術式です。
耳前瘻孔
耳瘻孔とは、生まれつき耳の周囲に小さな穴が開いて、その下方に管(または袋)があり、その管の先端は耳介軟骨で終わっているものを言います。これは耳を形成する時の異常により生じたものと言われています。耳の異常の中ではかなり頻度の高い疾患の1つです。遺伝性のみられるものもあります。
耳瘻孔から臭いのあるチーズ様の分泌物が出てきたりすることもあります。この状態で一生経過することもありますが、この小さい穴から細菌が入って感染を繰り返す場合もあります。一度感染を起こすと、その腫脹したところを切開して膿を出したり、抗生剤を内服するなどの治療が必要になります。慢性化すると耳前部や耳後部に膿瘍(不良肉芽)がみられることがあります。また、耳瘻孔のある方の顔面が感染により腫れたりすることもあります。このような病変を認めた場合、瘻孔を切除摘出することで治癒します。
嵌入爪・巻き爪
巻き爪は Pincer nailとも呼ばれ、爪甲の横彎が強くなった状態をいいます。巻爪はその名の通り、形態的に爪が横方向に湾曲した状態をいい、炎症、感染は普通ありません。爪の変形が高度になると爪が皮膚に刺さって、疼痛や側爪郭の発赤腫脹、感染、不良肉芽などの症状を生じます。主に足の親指が罹患しやすいです。足の形や、歩き方、靴の選択など種々の要因で爪の両側が皮膚に入り込むことで、炎症、感染を起こします。
治療には保存療法と手術があります。前者は超弾性ワイヤー(クリップ・プレート)やテープ・コットンパッキングを用いて爪矯正を行う方法で第一選択として行われるようになりました。
手術療法は、陥入している爪の端と爪母(爪を作り出す組織)を除去することによって、爪の幅を狭くして、変形や食い込み部分をなくす根治的治療です。様々な手術方法がありますが、最近では、より侵襲の少ないフェノール法が広く行われています。指の局所麻酔による日帰り手術で、手術直後から歩行できます。
口角炎
口の端っこに有痛性の炎症、皮疹が生じ、口が開けにくくなったり、食べる度に口角が切れて痛かったりします。
そんな口角炎の原因
①
カンジダ感染
免疫力の低下した方(高齢者・糖尿病、肝疾患、HIV感染症、副腎皮質ステロイド内服や免疫抑制剤による治療中、疲労や過度のストレス)が発症し易く、真菌であるカンジダ菌の感染により口角炎になることがあります。
②
栄養不足
ビタミンB2、B6、B12の不足で口角炎が起こりやすくなります。鉄分・亜鉛等のミネラルの不足も原因に考えられています。
③ 単純ヘルペスが関与している場合もあります。